
「ちょっとマイペースなだけなのかな?でも・・・」「神経質で怖がりさんなだけかもしれない」「イヤイヤ期の子供ってこれが普通なのかしら?」
乳児(0歳から1歳まで)を過ぎると、自閉症ではどのような特徴となって現れてくるのでしょうか?
赤ちゃんの頃は「赤ちゃんってこんなものなのかな」と気になっていなかったことも、だんだんとその子どもなりの気質が見えてくるのが幼児期です。
筆者の子供は、高機能自閉症です。
思い返してみると、あれ?という「いわゆる自閉症っぽさ」は2歳半よりあとの「幼児期」に気づくようになりました。
以下の記事を読んで「早期発見・早期療育」の参考にしてみてくださいね。
自閉症の子供は人のかかわり方の質的障害があります
後追いや人見知りをしない

幼児期の自閉症では、後追いや人見知りをしないことがあります。
これは人のかかわり方の質的障害があるためです。

-
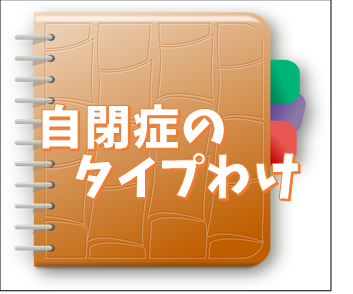
-
自閉症のタイプは【社会性の特徴】別でわけます【4つ】
こんにちは。 自閉症の息子を育てている ぴょんたろうです。 皆さんは、このようなことを思ったことはありませんか? 自閉症にもタイプがあるってきいたけど・・・? ...
続きを見る
具体的には、次のような行動がみられることがあります。
✅お母さんが視界から消えると泣くのに
お母さんといったん離れてしまうと
お母さんを思い出して泣いたりしない
「ケロッとしておとなしく遊んでいる」
✅離れるときには大泣きした割に
幼稚園にお迎えにいっても
「お母さんに会えた喜び」などの反応が薄い
✅抱っこを予期して「手をのばしたりしない」

また、特定の「ひげや眼鏡をかけた人」などを極度に怖がったり、後追いや人見知りが反対にとても激しすぎて、いつも一緒にいないお父さんに会うと大泣きする場合もあります。
お母さんを求めたりする行動の乏しさがないか?奇妙さ・極端さはないか?チェックしてみましょう。
自閉症の子供は一方的な関わり方をする特徴がある

幼児期の2~3歳くらいになると自閉症の子供でも、前述の「人のかかわり方」の質的障害は発達とともに軽減されることがあります。
すると今度は「人への関心や注目」が保てている子供でも、自閉症の特性のために今度は「一方的な関わり方が目立って」くることがあります。
代表的なものに「クレーン現象」と呼ばれるものがみられることがあります。
クレーン現象とは「人の手を道具のように扱う」ことです。
具体例としては
✅モノを取ってほしい方向にお母さん(他者)の手を投げる
✅人の手をUFOキャッチャーのように使って何かをしてもらおうする
✅人が「誰であるか?」わかっていないかのように、誰彼かまわず人の手をひいて
自分の要求をかなえるための手段として手を道具のように扱う
自閉症の子もには運動発達が偏っている特徴があります
自閉症の子供はハイハイをしないことがある

自閉症の子供では、運動発達に独特の遅れや偏りが見られるという症状があります。
ずりばいだけで、ハイハイをしないで急に立って歩くようになったり、2~3歳まではハイハイしていたのに、急に立って歩くようになったりなどです。
発達障害の不器用さ【発達性協調運動障害】の記事はこちら。
自閉症の子供は想像力(イマジネーション)の障害がある
自閉症の子どもはおもちゃを正しい使い方で遊ばない?!
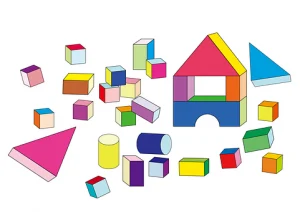
自閉症では想像力の障害があります。
このため、自閉症の子供には「おもちゃをおもちゃ本来の使い方で遊ばない」特徴が見られます。
さらに、感覚を刺激する楽しみのためだけにおもちゃを使います。
ごっこ遊びや、見立て遊びなどの発達が定型発達の子どものように発達しません。
テレビや本の主人公や、鉄道や生命のないものの「セリフを真似したり」します。
なぜかというと、想像力の障害という特徴があるためです。
筆者の子供は高機能自閉症です。
買い物に行くとカートの横に寝そべってカートのタイヤを手でもてあそんでいました。
具体例としては
✅自転車の車輪をひたすら回して眺めて遊ぶ
✅水をまいて遊ぶのが好き
自分自身が「生命のないもの」になり切って遊ぶこともあります。
モーター音や機械音の音の真似をしたりします。
想像力を使った見立て遊びではなくて「そのものになり切っている」ようなイメージです。
見通しが持てないことに不安になる・泣く特徴がある

自閉症では「想像力の障害」があります。
私たちは目に見えない・実在しないものを「ああかな?こうかな?」と想像することで、ある程度の予測をたてることができます。
それをもとに、一日に何百回も行動を決定・選択しているのです。
ですから、「想像力の障害」がある自閉症では自分(子供自身)の予測していた通りに物事が進まないと不安になって泣いてしまうのです。
反対にいうと、見通しがあってその通りに物事が進むと自閉症の子供はとても安心します。
・運動会・参観日などの行事
・手順が違っている(道順なども)
・日常のルーティンが崩れる
このような変更などでも自閉症のパニックの引き金になってしまいます。
自閉症の子供はマイルールにこだわる(秩序を守りたい)

自閉症の子供の特徴に、自分で決めたルールを守ることが強いこだわりとなって表れることがあります。
なぜかというと、自分の世界の秩序を守ることで安心したいからです。
これは想像力(イマジネーション)の障害が原因の場合もあります。
想像力の障害がありますと、想像しなくても自分でコントロール可能なことを好みます。
・必ず一番最初か最後に部屋に入るこだわり
・座る場所を自分が決めるこだわり
子どもによってこだわりは様々なのですが、上記のように「自分でコントロールしようとする」ことで、想像しなくても一定の秩序が得られますから、子どもの中で安心感につながります。
このルールが強くなってこだわりのように見えるのです。
日常生活の何がこだわりになっているか?というのは「そのものごとができないときに、パニックになってはじめて気づく」こともあります。

気づかないこともあるよ。
変更されてパニックが起きてはじめて「こだわり」に気づくみたいな。
変更や不測の事態でパニックになる
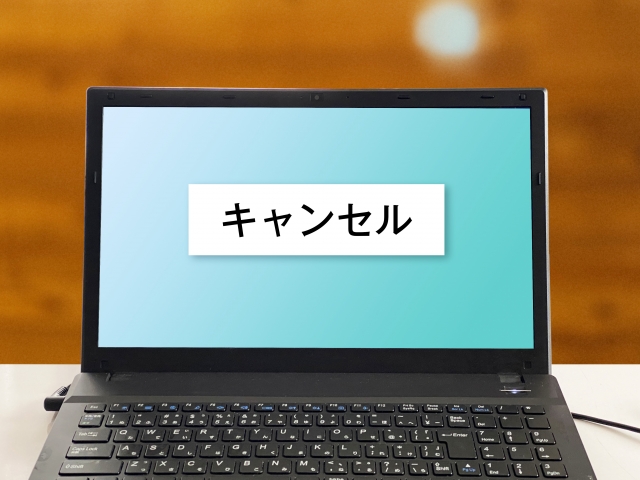
自閉症では変更という変化が苦手でパニックになることがあります。
世の中は「思っていた通りにものごとが進んだり」することは少ないですよね。
そのため、私たち人は、その場に応じて変更などを受け入れて臨機応変に行動しています。
ですが、自閉症の子供ではその場その場の状況に応じた臨機応変の対応が難しいです。
これは想像力の障害のためです。
変更があるということは、新しいプランを立てて「違う結果が起きる」ことを予測しなければなりません。
変更によって「違う計画を立てる」ときには、想像力は欠かすことができません。
ですが自閉症では「想像力の障害」があるために計画や見通しを立てることができないのです。
そのため、想像力の障害がある自閉症では、変更に対応できずにパニックに陥ってしまうのです。
こだわりへの育児方法については以下の記事をごらんください。
-

-
【自閉症】こだわりへの対応ってどうすればいい?解説します
このような悩みはありませんか? 悩む人「自閉症のこだわりやかんしゃく無理ゲーすぎ 」「どうやって育児したらいいの?」 自閉症にはこだわりと呼ばれる行動があります。 結論、こ ...
続きを見る
新しいことに挑戦したがらない(いつもと同じがいい)

自閉症の特徴である想像力の障害が、新しいことに挑戦したがらないという症状として現れることもあります。
私たちは、新しいことをするとき無意識に「今までの経験を想像」して推測しています。
遊園地のジェットコースターに乗るときも、今までに乗ったことがあるので「どんな体験が訪れるか?」想像します。
コンビニエンスストアで新商品のお菓子が置いてあるときもそうです。
パッケージに書いてある商品名の材料や絵から「どんな味なのか?」想像することで「美味しそうだな」と感じて食べたくなり購入します。

ですが、食べたことのないものは「想像力を使って」味を予測するしかありません。
できごともそうです。体験したものは、今までの経験から似ている体験を想像するしかありません。
想像力の障害がある自閉症の子供は、その想像力の障害があるために予測ができません。
そのため「新しいできごと・食べ物」にとても不安を感じるのです。
それが新しい体験を嫌がる(挑戦しない)ことにつながってくるのです。
こだわりが見られるか?些細な変更にパニックになるか?いつもと同じことをしたがるか?チェックしてみましょう。
自閉症の子供の会話はエコラリア(オウム返し)が特徴的です

言語発達に遅れのないグループであるアスペルガー症候群では、出ないこともあります。
自閉症の子供には常同運動が見られることが多いです

自閉症の特徴として、常同運動という症状があります。
具体的には
✅くるくる回る
✅ぴょんぴょん跳ねる
✅手をひらひら・パタパタさせる
✅体を揺する
✅つま先で歩く
これらを「常同運動」といいます。
感覚刺激と深く関連があります。
感覚刺激への没頭は乳児期でも見られます。
「ストッキングを触る」「紐をふる」「匂いをかぐ」」などもそうです。
自閉症の子供は自分の感情を把握するのが苦手
自閉症の子供は自分の感情を把握するのが苦手という特徴があります。
自分の感情に気づくことが難しいのです。
これはなぜかというと、自閉症では「概念化が苦手」だからです。
感情は「悲しい・悔しい・こわい・嬉しい」などのように単純なものだけではありません。
嬉しいときも泣きますし、悔しいときも涙が出ます。
嫉妬心や猜疑心、驚いて怖かった、がっかりしたなどのように、感情は一言では言い表せないものが多いです。これらの感情を細かくわけていては大変です。
ですから私たちは、大きくわけて「概念化」をしてカテゴリわけしています。
「マイナス感情」「プラス感情」ネガティブ、ポジティブなどのようにざっくりわけたり、「落ち込んだ時の感情」「嬉しいときの感情」などのようにわけたりもできます。
ですが、自閉症では感情の構成している一つ一つは認識できるのに、うまくまとめること(概念化)が難しいのです。
例えば「失笑」「苦笑い」の感情は決して「嬉しい気持ち」ではありません。「緊張」などの身体感覚を言葉でまとめることも苦手です。
このような細かい感情は「どのカテゴリ」としてまとめればいいのか?感情をわからないですし、自閉症の子供にとってはまとめることがとても難しいのです。
怒っているのに「ニヤニヤしていたり」自分が、つらいのに平気な顔をしてたりすることもあります。
【参考】自閉症の息子は怒られても笑う子だった【絵で具体的に教えよう】
-

-
自閉症の息子は怒られても笑う子だった【絵で具体的に教えよう】
こんな悩みを感じたことはありませんか? 悩む人・うちの子は叱っているのに笑っている(ニヤニヤしている) ・反対に優しく注意しただけなのにすごく怖がる・・・ ・困っているとき ...
続きを見る
自閉症は物を並べたがる・集めるのが好き

(画像は息子が並べた車です)
自閉症の子供では1歳半を過ぎたあたりから、物を一列に並べたり、電話帳を眺めるという行動が多く報告されています。
興味の幅が狭くて限局的で、自分なりのルールを決めたがります。
そのような狭い範囲の興味へのこだわりは、以下のような形であらわれます。
・おもちゃの並び方にこだわりがある
・同じメーカーのお菓子や食べ物しか食べない
・電車やカレンダーの数字へのこだわり
まとめ

自閉症の幼児期に見られる特徴は乳幼児に見られた「感覚刺激への没頭」「目をあわせない」などに加えて
自分の世界でのルールに固執することがこだわりになっていく特徴があるです。
幼児期になると、お母さんも育てにくさに気づいていく頃だと思います。
ですが、それが「イヤイヤ期」と重なるために「障害なのか?「単なる発達の過程であるのか?」わからないことがあるのではないでしょうか。
こだわりが想像力の障害からきていそうだと感じたり、感情の把握などに違和感を感じたら、一度相談にいってみるとよいと思います。
参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
-

-
自閉症の赤ちゃんの頃の様子【5つ】当てはまってない?
育児をしていると気になるのが、子どもの発達ですよね。 悩む人「私って育児下手なのかな?」 「私が神経質なだけなの?」 「障害なの?それとも個性の範囲?」 ママ友に聞いても「心配しすぎ ...
続きを見る


