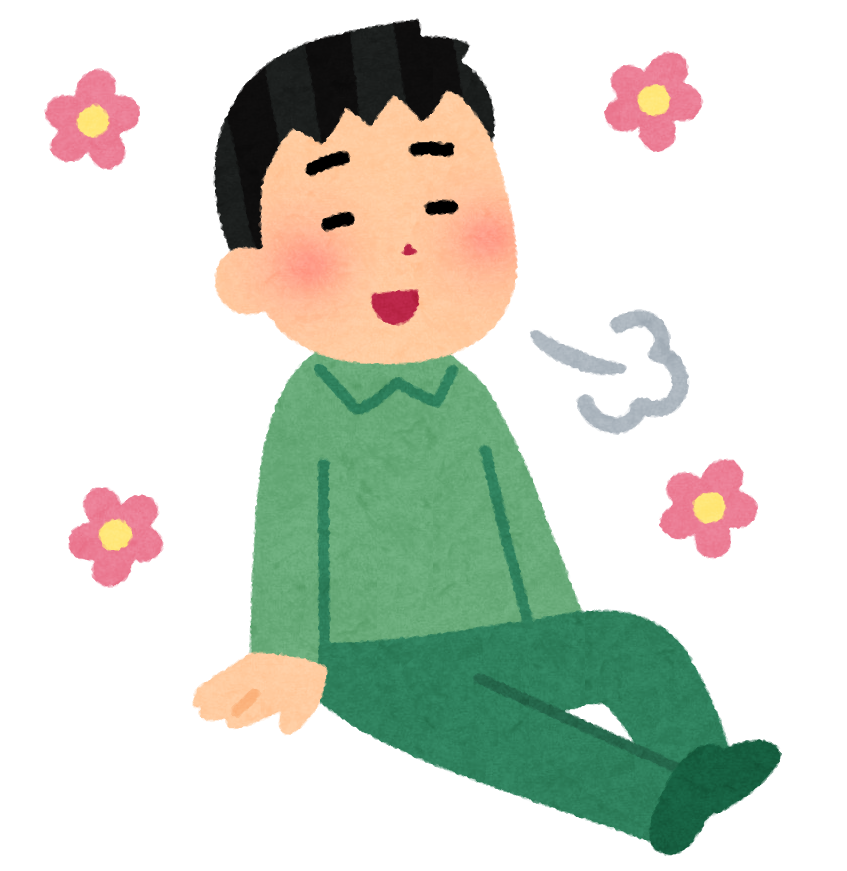発達障害の子供を育てているみなさん、育児、頑張ってますか?

自閉症の親ってやることいっぱいありますよね。
しかし、支援を始める前に一番大切なことがあります。
自閉症の子供の育児は安心感が基本です。
子供の日々の生活の安定ですね。
私たち定型発達にとってはなんでもないことも、自閉症の子どもにとっては思っている以上に不安になりやすいのです。
特に見通しなど「わからないこと」が不安につながりやすいです。

今回の記事は「自分の頑張るモチベーションをあげるため」に自戒しつつ書きます。
簡単な流れ
- 子供を家庭に合わせるのではなく、家庭(親)が子供によりそって合わせる
- そのためには、親の理想はいったん崩してあきらめる
- 子どもの「わかってもらえている感」を大事にする
- 子どもに伝わりやすい方法で伝える
- 子供が実行できるようにサポート(伝え方)する
発達障害の子供が安心できる環境「日々の暮らし」の作り方
親(大人)が発達障害の子どもの世界にあわせる(寄り添う)

まず、わたしたち大人が自閉症の子供にあわせていく・寄り添うような視点を持つことが1番目です。
自閉症の子供を親の方針にあわせて育てるのではありません。
それについて、佐々木正美先生はこのように述べておられます。
「子どもの特性に合わせて、家庭を変えていく」
(佐々木正美著、アスペルガー症候群・高機能自閉症の子どもを育てる本、P12より)
どうしても、親は私も含めて大人のほうで決めたルールを子どもに守ってもらおうとしてしまいます。
そして

となってしまいます。
親の子育ての理想は捨てる

佐々木先生は続けます。
「親として子育ての理想形をもちその形に子どもを従わせるのはやめましょう」
(佐々木正美著、アスペルガー症候群・高機能自閉症の子どもを育てる本、P12より)
要するに「こういう風に育てたい」という理想を自閉症の親は捨てるべきだとおっしゃっています。
これについて、私はどう思うかといいますと、まあ、そうですよね、
結局のところ、「理想」って頭の中にあるわけで現実を見るのと対局でして、最も「現実から遠い」わけです。
地に足がつかないといいますか、早い話がただの願望なわけです。
厳しいようですが、そのように考え方を変えなければ親も病んでしまうし子どもも辛くなるというとだと思います。
子育て環境が安心どころか親子にとって地獄のような日々になってしまうからです。
自分もそうだったことがあるので、本当にわかるのですが「理想」を持つのは大事なんです。
しかしそれって、自分の目標設定で使うからいいのであって、人格も性格も違う子どもの育児に「理想」を求めても辛くなるだけです。
自閉症の子に寄り添うことは、「自閉症の親の理想を捨てる」こと・・・?

(画像はイメージです)
私の子供は幼稚園のころ、よく道路でよくねそべっていました。
スーパーでも歩きたくなければ寝転んでしまって歩いてくれません。
もうその場合は、「買い物にいく」「子供が興味のない買い物に子どもを連れていく」ことをあきらめるしかありません。
だからといって留守番をさせるわけにもいかず。
値段は高いですが、宅配サービスを利用していました。
(生協さんやパルシステムさんなどです。)
これもある意味、「理想を捨ててる」と言えると思います。
子どもと手をつないで楽しく買い物しながら、「野菜の種類を覚えたり」など新しいことに触れさせたりなどの余裕はありませんでした。
他にもこんな親自身の理想をあきらめなければなりません。
- 公園で親子仲良く遊ぶ。
- 家族で外食を楽しむ。
- お友達とわが子が楽しく遊んでいるのをほほえましく見守る。
- 抱っこして「ママ好き」といってもらうこと。
- (普通に暮らすこと)
書いてみても、理想というほど贅沢ではないと思うのです。
つまり普通ですよね。
それってどういうことか?といいますと自閉症の親にとって普通の暮らしが「理想」と思えるほど、大変ということです。
そして、「理想を捨てたほうがいい」のですから、「私たち自閉症の親は普通のことすら求めてはいけない」ということになります。
(自閉症で有名な佐々木正美先生の言う理論だとそうなります)
自閉症の親は「普通」のレベルをかなり下げて妥協しなければならない。
理想を捨てるとあるがままの自分や相手を受け入れられるようになります

「自閉症の親は理想(ここでは普通のことだけど)ではなく、子どもに合わせていきましょう」と佐々木正美先生はおっしゃるわけです。
(;´・ω・)
これは、厳しいように見えて親子を救う言葉だと思うんですよね。
結局のところ、理想ばかり追いかけていると現実がそれに追いついていないと、その「理想と現実のギャップ」がよけいに不幸感を生んでしまうからです。

結局、親が考える理想って「こうなったらいいな」の押し付けに過ぎないのですから。
子供の世界に親が主体的によりそう、子供にまずは歩み寄ってみる決意と自覚を持ってみてください。
まず何かを変えるには、「決めること」が大切です。
自閉症の子どもが安心できる環境は「安心できる人」がいること
自閉症の子どもが「自分のことをわかってもらっている」と感じることを目指す


次にするのは、「親は自分のことを親はわかってくれる」という感覚です。
自分のことをわかってもらっていると自閉症の子ども自身が感じることが「安心感」につながります。
それを目指しましょう。
子供が安心して過ごせると感じていれば、発達障害の子供も家庭生活が「安定」します。
自閉症の子どもの心の安心感が日々の暮らしの安定につながるのです。
そして、自閉症の子どもが安定してくれば私たち発達障害の親も心が安定すると思います。

私は14年間、自閉症の子供を育ててきましたが、経験上、やっぱり親である私が先に安定していると子どもも落ち着きやすいのは確かだと思います。
これはですね、親の精神が安定してるとパニックを起こさない安定するということではないんですよ。
パニックや癇癪は普通におきます。
ただ、子どもが安心してパニックを起こせてるといいますか・・・
そのあと自分で立て直せるようになるのが早いという感じでしょうか。
えっとですね、体験談なんですけど。
ときどき、ゲームの癇癪で息子が暴言を吐いたときに、私が気づいてちらっと息子を見ます。
すると目が合ったので私は「苦笑い」をします。
すると、息子もちょっと冷静になったのか「自分が言った暴言を恥ずかしそう」な感じになって、ゲーム相手へ暴言を吐くのは続けるって感じですかね。
続けるけど、あきらかに暴言の怒り度は弱まりますね。
うーん、説明が難しいのですが例えるとですね。
「なんだよ!!くそ!!この自動販売機!!壊れてんのか!!くそ!!」って貴方がブチ切れているとします。
そこに仲良しのママ友が通りがかって「どしたの?(笑)」ってなったときにどんな感じになりますか?
「いやあ~あのさー(苦笑)本当この自販機クソだわー-。さっきから使えないのよ!!1000円も入れたのにおつり出ないんだよねー-(苦笑)
くそっお金泥棒が!!(笑)(怒)いやもうこんな感じよ?!(笑)(怒)」
って説明しつつ、暴言は吐き続けるみたいな感じです。
伝わりますかね?
でも、一人で怒っていたときはガチ目に怒っていたのに、少しだけコントロールされているようないないような。
そんなイメージです。
次に自閉症の子どもが理解できる伝え方になっているかチェックする

自閉症の子どもが安心して暮らせるためにするために次にすることは、身の回りの情報を理解できる形で伝えているか?チェックすることです。
子供が安心して家庭生活を過ごせるようになるためには「子ども自身が理解しているか」が安心につながります。
想像してみください。

発達障害では想像力の障害があります。
ですから何が起きるのかわからない、具体性に欠けるものは想像力がいりますので不安になります。
プレゼントやいい意味でのサプライズも「わからないまま驚かされる」のはたぶん苦手だと思われます。
自閉症の子にとっていい意味での変化・変更だとしても、たぶん不安につながると思うんですよ。
- 具体的か?
(ちょっと、もう少し、ちゃんとなどはわからない) - 簡潔か?
(必要なことだけ話す) - 見て確認できるようになっているか?
(絵や写真・見本などの補助) - 順番は明確にわかるようになっているか?
(順番をつたえる・はじめと終わりを伝える) - 肯定的に伝えているか?
(「だめ」「やめて」ではなく何をどうしたらいいのか正しい行動を示す)
場合によっては構造化も取り入れて子どもが安心できる情報の伝え方を意識してみてください。
子供が安心して「実行できる」ことで自己効力感を高める

伝え方を工夫して「肯定的に伝える」ことを意識していれば、子供は「実行できる」可能性が高まります。
プロンプトや自発を教えようとすると、ABAの勉強から入らなければならず「やりながら親が学ぶ」ことが遅くなります。
特にABAは親ひとりでは難しいので専門のセラピストにアドバイスを受けながらが望ましいと思います。
とはいっても、セラピストに来てもらうと1時間、1~3万円すると思うんです。
そうすると指導してもらうだけで発達障害の療育で月に何万円もとんでいくので、自閉症の親は無理ゲーとなります。
ですが、構造化や視覚支援は親がやろうと思ったら100均の材料でもできますし、ハードルは低いと思います。
経験則ですが、私は何もわからないまま、理論がわからないことが多いのですが、見様見真似で形から入ってやっているので全然OKというスタンスです。
実際に、スケジュールも形にして子供に使ってもらわなければうまくいくのか・いかないのか?何がうまくいかないのか?わからないので。
ざっくりと切り出してから、調整みたいなイメージです。
その細かい調整の部分は、子どもにあってないといけないので先にやることが不可能なんです。
先に見立てだけで、その子に完全にフィット感のあるものが作れたら、たぶんその人は天才です。
見よう見まねでやってみてから、微調整する。あるいは詳しい人に「どうですかね?」と聞いてみる。
まとめ
発達障害の子どもが安心できる家庭生活のためには
①子供を家庭に合わせるのではなく、家庭(親)が子供によりそって合わせる
②そのためには、親の理想はいったん崩してあきらめる
③子どもの「わかってもらえている感」を大事にする
④子どもに伝わりやすい方法で伝える
⑤子供が実行できるようにサポートする