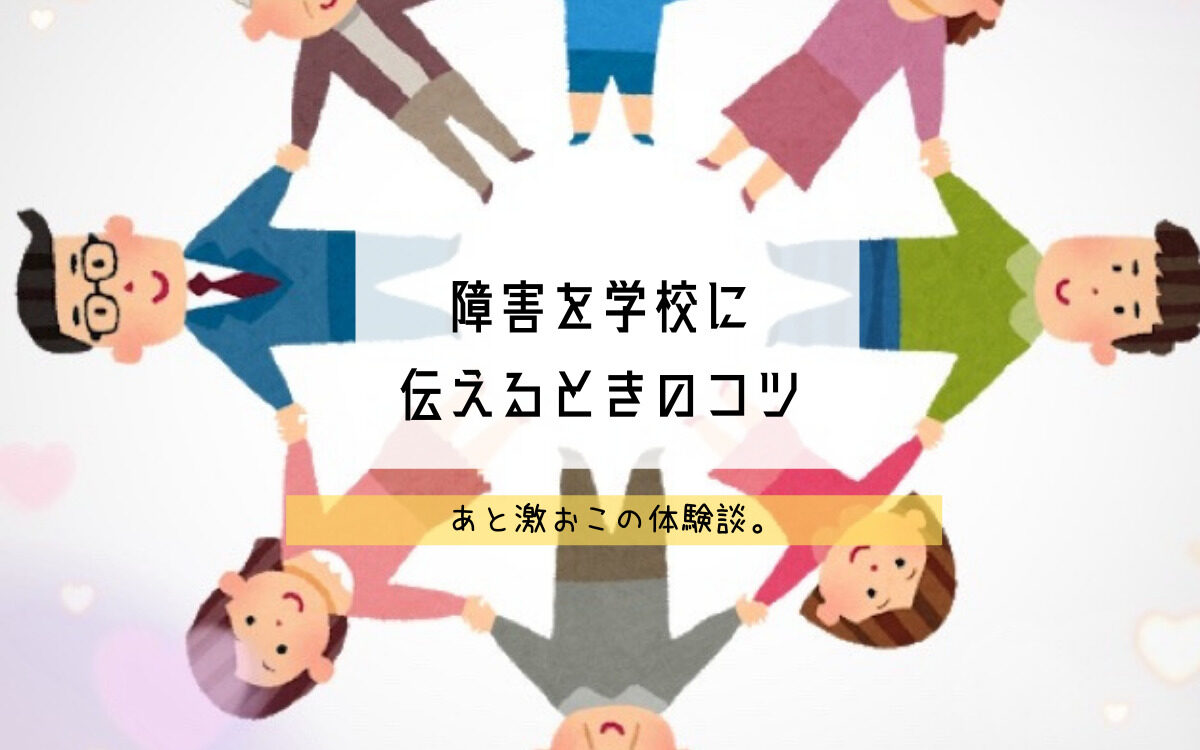筆者の息子は注意力の転導(注意散漫)が強かったり、力の入れぐあいのコントロール、指先や体を協応させて動かすのが苦手な症状(発達性協調運動障害)の診断も受けています。

はい。
つまり、ちょっと自閉症スペクトラムに加えてADHDの傾向があるねと医師に言われています。
今回は、そんなADHDの「不器用さ」の具体的な症例とその対策について、この記事を読んでくれているみなさんと楽しく勉強していきます。
ADHDの経営者になれる長所は以下の記事をごらんください。
ADHDの長所4つは経営者むき!!知ればあなたの才能になります【自分を知る】
【ADHD】の子供 不器用で起きること
ADHDの子どもは、うまくお箸が使えずに食事のときにこぼしまくる

ADHD傾向があると、お箸がうまく扱えません。
そのため、食事のときにぼろぼろこぼれます。
他には
- くつひも・はちまきがうまく結べない
- ボタンをとめるのが苦手
これもお箸のように、指先を上手に使う必要があります。
なぜ、指先をうまく使うことが苦手なのかというとADHDでは運動発達の異常があるからです。
これらは「微細運動」といいます。
微細運動と祖大運動についての記事は別の記事をご覧ください。
【参考】なわとびがうまく飛べない!自転車やダンスが苦手なのは【発達性協調運動障害かも!】
現在、小学校5年生の息子は小4の終わりくらいに靴のひもを結べるようになりました。
なわとびが苦手・ブランコがタイミングよくこげない

ADHDでは目・指先や筋肉の動きの連携がうまく行われないために、細かい作業が苦手です。
他に、なわとびやブランコも苦手です。
なわとびは
①「なわを回す」(手首のスナップを使ってうまく回転させる)
②「タイミングよくジャンプする」
という、動作が組み合わさっています。
長縄跳び(大縄跳び)で考えると、縄を回す人とジャンプする人のタイミングや動きがバラバラになることがあります。

そうです。こんな感じのことが、ADHDでは一人でも起きるので、とても難しいのです。
ブランコも難しいですね。
縄跳びとは種類が違いますが、息子がブランコがこげるようになったのは小学4年生の5月ですね。
驚かれるかもしれませんが、筆者の息子はローラーブレードは上手に滑れるんですよ。
自転車も乗れるようになりました。
(^o^)/
どうやらADHDだからといって「運動がまるきりだめ」ということではなく個人差があるようです。
筆者の息子はバランス感覚がよかったのでしょう。
扉を乱暴に閉める(力のコントロールの加減ができない)
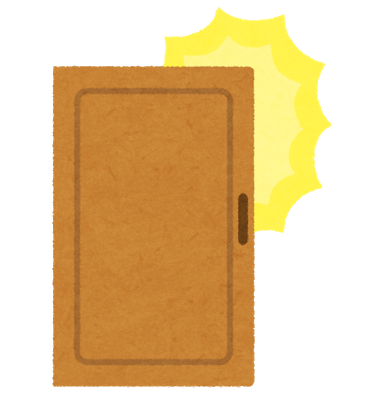
不器用さがあると扉を勢いよく閉めます。
我が家のお風呂場のドアはかなりの頻度ではずれます。
私は家にある色んなものが壊れていく。
・・・ので、発達障害の専門家であるK先生に

という疑問をぶつけてみたことがあります。
すると、K先生はこう仰ったのです。


そう考えるとADHDは「乱暴」というのは、人格的な評価であってそれは「誤解」だと気づきました。
ADHDは指先から、ありあまるエネルギーが爆発しているだけだとその時気づいたのです。
字を書くのが苦手
ADHDは字を書くのも苦手です。
なぜならば、K先生から教えてもらった「指先からほとばしるエネルギーをうまくコントロールできないから」です。
ですから、筆者の息子の鉛筆は、かなりの頻度で芯がバキ折れます。
力のコントロールが苦手なのですから、調子の悪さでみみずのような弱弱しい文字を書く時もあります。
この息子の「筆圧が濃いときもあれば薄いみみずのはったような文字の時もある」という字のうまい下手の差があることを、残念ですが学校の先生は理解できないようでした。
ふざけて字を書いていると思われて「字を真面目にかきましょう。宿題を全部やり直し」
と赤ペンで書かれてしまったことがあります。(泣)
その時の記事は以下を参照ください。
【げき怒事件】障害を学校に伝えるときってどうすればいいの?【コツを解説】
(;´・ω・)

これもわかりにくいのですが誤解です。
できる時とできない時の差が大きいのも発達障害の特性の一つです。
力のコントロールが苦手なため手先を上手に動かすのが不得手なのです。
決してふざけているわけではないのです。
- ADHDの子供は乱暴じゃなくて「力のコントロールが苦手なだけ。」
- ADHDの子供はふざけているように見えるのは誤解。
ADHDの不器用さの改善方法
不器用さの改善方法①迷路で鍛える
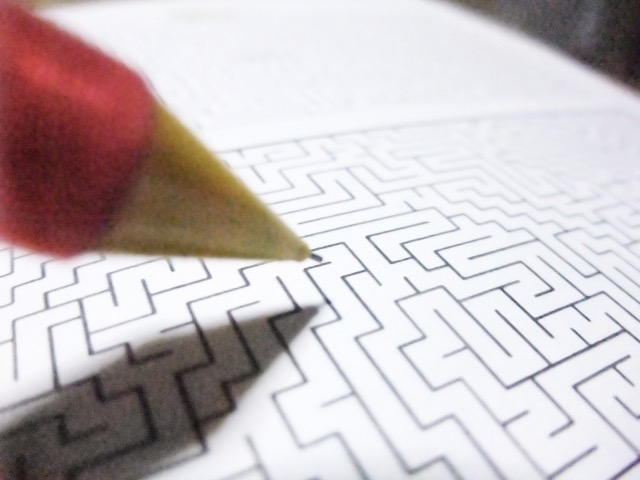
迷路をなぞるという方法があります。
これは「目で見たものと指先の動きを協応(連携)させる」という発達を促すことができます。
もちろん、漢字などをなぞって書いたりするものでもOKです。
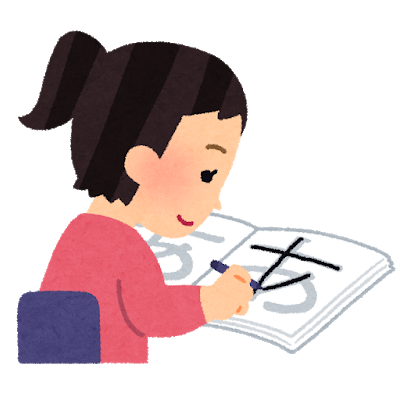
ですが、個人的には迷路のほうが楽しく取り組めると思うのでオススメです。
ADHDの不器用さの対処法②粘土で鍛える

粘土では指先の感覚を育てることができます。
丸める、伸ばす、ちぎるといった動作を繰り返すことで指の細かい使い方や力の入れ方の練習につながります。
小さい〇を粘土で作ってもらうとわかるのですが、指先に力を入れすぎるとつぶれてしまいます。
これで力のコントロールの加減を身につけます。
ADHDの不器用さの対処法③切り絵で鍛える

切り絵をすることで、はさみの使いかたや工作などの練習になります。
「切る・張る・描く」などができればお子さんのお好みで用意してあげてくださいね。
まとめ
不器用さは手の動きと目の動きがうまく結びつかないという背景があります。
不器用というと、祖大運動ではなく微細運動が問題になりがちですが粗大運動(体を大きく動かすようなもの)も発達していないと細かい動きも難しかったりします。
ですので、どちらもバランスよくお子さんのできるレベルに合わせて、迷路や工作、1ページ、5分から取り組んでみてください。